「変えずに変える」 老舗120年のDX共創

明治38年(1905年)創業の一澤信三郎帆布(京都市)は、「時代に遅れ続ける」ことにあえてこだわり、手書きの手紙や修繕対応など、人の手による丁寧な顧客対応を大切にしてきた企業です。そうした“変えたくないもの”を守りながらも、業務効率と顧客接点の質を高めるべく、同社はフューチュレックとともにDXに着手。紙ベースで行っていた受注・在庫・製造管理を、現場に寄り添うかたちでデジタル化しました。
今回、取締役・一澤佳織氏とフューチュレック神田による対話を通じて、伝統を損なわずに変化を受け入れるプロセスをひもときます。
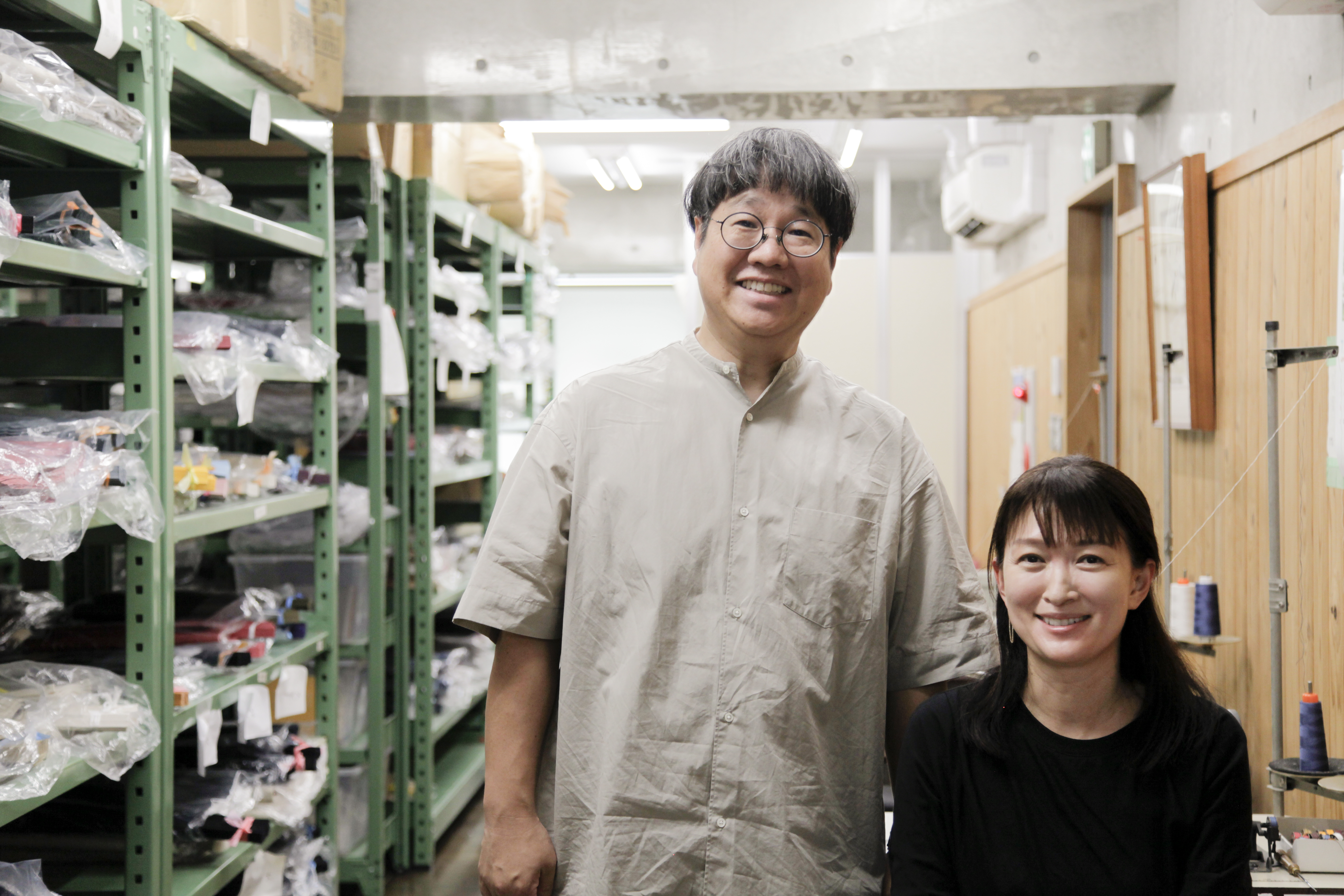
右:一澤信三郎帆布 一澤佳織さん
左:フューチュレック 神田
1. はじまり|受け継いできたものと、変化を考えたきっかけ
まずはじめに、一澤信三郎帆布として、創業以来大切にしてきた価値について教えてください。
私たちは創業以来、「良質な帆布を使った丁寧な手仕事」「修繕をしながら長く使っていただくこと」、そして「京都で作って京都で売る」という三つの柱を大切にしてきました。これらはどんな時代であっても、決して揺らぐことなく受け継いできたものです。お客様の生活に静かに寄り添いながら、長く愛されるものづくりを続けてきたという自負があります。
そのような伝統のあるブランドが、DXに踏み切るというのは大きな決断だったかと思います。きっかけは何だったのでしょうか?
正直なところ、すべての業務が紙ベースだったことに限界を感じていました。顧客情報も受注管理も修繕記録も、すべて手書きで管理していたんです。ファイルが見つからない、バインダーの綴じ方を間違えてしまう、そういった小さなトラブルが積み重なる中で、「このままではいけない」と思うようになりました。
しかも、お客様の中には、わざわざ現金書留で注文書を送ってくださる方もいて。本当に有難いのですが、それだけのご負担をおかけしていたのかと思うと、今の時代に合った手段を整える責任も感じるようになったんです。

全ての製品は工房でひとつずつ丁寧に作られている
初めてフューチュレックにご相談いただいたときのことを覚えていますか?
はい、とても印象的でした。私たちは“システム開発の会社”というイメージで問い合わせをしたのですが、フューチュレックさんは最初のヒアリングから、私たちのこだわりや歴史、現場の空気感に深く耳を傾けてくださった。こちらが1を伝えると10を理解してくれるような、そんな感覚がありました。

2. 共創のプロセス|「変えずに変える」ための対話
フューチュレックとの取り組みは、どのように始まったのでしょうか?
ご相談をいただいたとき、正直かなり緊張しました。有名な京都の老舗企業からのお声がけというだけで、背筋が伸びるような感覚がありましたね。でも、お話を伺ううちに、課題は非常にクリアで、「これは私たちがお力になれるはず」とすぐに思いました。
とはいえ、老舗企業ならではの文化や空気感があることも肌で感じていて、「これは一筋縄ではいかないぞ」と、ある種の覚悟を持ってプロジェクトに入りました(笑)。だからこそ、“変えること”よりも“変えないこと”をどう守るかを常に意識しながら進めていきました。
紙の業務フローをデジタルに移行するなかで、どんな課題がありましたか?
やはり、歴史がある分、社内には強い“変化への抵抗感”がありました。職人たちは、自分たちが目で見て、手で触れて、体で覚えてきた感覚を大事にしてきた人たちです。それが、数字で管理される、パソコンで指示されるとなると、「自分たちの仕事が否定されている」と受け取られてしまった面もあったと思います。
あるとき、「まるで黒船」と言われたこともありましたし(笑)。同時に「俺たちはロボットじゃない」と言われたこともありました。真剣に向き合っているからこその言葉だと受け止めています。
「らしさ」が否定されるようなシステムにしてはいけない、と私たちも強く感じていました。システムはあくまで人の営みを支える道具であって、主役ではありません。職人さんの感性や誇りをどう守りながら新しい仕組みを届けるか、何度も話し合いながら模索しました。
反発があった中で、どうやって打開されたのでしょうか?
現場との対話を続けるなかで、ある日社長が職人たちに言ってくれたんです。「現場を見ずに判断するのは怠慢や」と。お客様と日々接している店舗スタッフが見ているものにもっと耳を傾けよう、というメッセージでした。その一言で、職人たちの意識が大きく変わったように思います。
それからは、私たちも「使いやすい環境を整えるから、ついてきてください」と腹を括りました。運用が始まると、「これ、早くて便利!」と現場からも声が上がってきて、いつの間にか文句は一つも出なくなったんです。むしろ、「ありがとう」と言ってもらえるようになったのは、本当に嬉しかったですね。

フューチュレックと進める中で、新しい発見や意外だった提案はありましたか?
とても印象に残っているのは、インターフェイスのデザインについて「毎日使うものだから、開いてワクワクする気持ちになるようにしませんか」と言ってくださったことです。最初は業務システムでそんなことまで?と思ったのですが、使い始めてみると、気持ちの面でも大切な要素だったと気づきました。
ちょっと“ワクワク”は大げさだったかもしれません(笑)。でも本気でそう思っていて、関わるすべての方が「これは自分たちのためのものだ」と感じられる状態をつくりたかったんです。よくあるのが、要件定義書通りに作ったのに、現場では「使いにくい」と感じられてしまうシステム。それって、結局は“自分たちのため”に設計されていないからだと思うんです。
だから今回も、一方的に“完成品”を押し付けるのではなく、皆さんと一緒に「何が本当に必要なのか」を考えながら、一緒に“つくっていく”プロセスを大切にしました。
発注と受注という関係を超えて、私たちと同じ目線に立って考えてくれるその姿勢に、信頼感を抱くようになり、安心して一緒に伴走していただけるとも思いました。
3. 成果と変化|静かに、でも確かに変わったこと
導入によって、実際の業務にはどのような変化が生まれましたか?
業務のスピードが上がっただけでなく、“余白”が生まれました。たとえば、これまで紙に書いていた時間を、お客様への手紙を書く時間に充てられるようになったんです。そこに、私たちらしい価値があると感じています。
あと、テレビで紹介されたときに、数千件の注文が一気に入ったことがあったんですが、あの時もし紙だったら……きっと捌けていなかったでしょうね。ブランドとしての信頼を守るためにも、デジタル化は欠かせなかったと今は確信しています。
弊社の作ったシステムが役に立ってることを実感できるのが嬉しいです。
まさかこんな老舗企業が店舗でiPadを使ってるなんて当時は誰もイメージしてなかったと思います。

お客様に“お便り”を送る気持ちで冊子『一澤だより』を制作。企画から記事執筆、写真撮影、誌面デザイン、さらには封入まで実施
4. 次のチャレンジ|守るものを見つめ直しながら、前に進む
現在取り組まれている新しいテーマについて教えてください。
今、ようやくクレジットカード決済の導入に踏み出そうとしています。以前は、「すぐ届く」という期待を持たせてしまうのではと不安で、導入できずにいました。でも神田さんに、「遅れ続けることと、不便を強いることは違いますよね」と言われて。はっとしました。確かに、今の支払い方法では、コンビニが近くにない方や外出を控えている方にとっては不便だと気づかされたんです。
今回は「ECサイトを作る」という話ではなく、“ブランドとしてどうあるべきか”を一緒に見つめ直すプロセスでした。時代に遅れ続けるという姿勢は大切にしながらも、お客さまに不便をかけないためには何を変えるべきか。たとえば、カートのアイコン一つにしても、「これはECらしさが出すぎないか?」と、細部まで丁寧に議論を重ねました。
実は、「変えること」よりも「変えないこと」の方が、ずっと難しいと思っています。新しいツールや仕組みを導入するのは簡単に見えるかもしれませんが、それが本当に自分たちの価値を高めるのか、本質を見極めることが何より大切だと感じています。
今後、さらに進めていきたいことはありますか?
顧客動向や売れ筋データをもとに、新しいコミュニケーションや製品開発につなげていきたいですね。おかげさまで三世代にわたってご愛用いただいていますが、新しい世代にも届けていくために、デジタルの力を上手に活かしていきたいと考えています。
僕も実際に使わせていただいて、本当に良いかばんだと実感しています。長く使えることの価値って、体験してみると想像以上なんですよね。そして、それを支えている会社の文化、たとえば、割に合わなくても修繕を続ける姿勢などに、心から敬意を抱いています。
それは単なるサービスを超えて、“使い手との関係を育てる姿勢”なんだと感じました。

世界にたったひとつのお店は国内外からのお客様で溢れかえっている。たくさんの種類があり、見てるだけでもワクワクします
5. おわりに|フューチュレックの存在とは
最後に、フューチュレックはどんな存在だったと思われますか?
私たちは、京都で120年、手仕事のかばんづくりを続けてきました。今も、手紙や電話といったアナログなやりとりを大切にしています。そんな私たちにとって、最先端の技術を扱うフューチュレックさんとの取り組みは、最初は正直、距離があるように感じていました。
けれど実際は、文化や考え方を丁寧にくみ取り、「変えずに変える」ための道を一緒に探ってくれる存在でした。押しつけるのではなく、隣で考えてくれる。ときには「それはやらないほうがいい」と言ってくれることもあるんです。時代の流れに乗るのではなく、「これは一澤信三郎帆布さんには合わないかもしれませんね」と、あえて立ち止まらせてくれる。それは、本当に私たちのことを思ってくれているからこその提案だと感じています。
私たちが“日々に寄り添うかばん”をつくるように、フューチュレックさんは“未来に寄り添うしくみ”を共につくってくれる。形は違っても、目指すところはきっと同じです。今では、本当に信頼できる、大切なパートナーだと感じています。
